社長・上原さんへ8つの質問
基本プロフィール

上原高志(うえはら・たかし)
| 1972年 | 8月28日東京生まれ |
|---|---|
| 1991年 | 東京都立両国高等学校を卒業 |
| 1995年 | 東京工業大学社会工学部を卒業 三和銀行(現三菱UFJ銀行)へ入行 |
| 2008年 | MUFG子会社の日本電子債権機構(JEMCO)を設立 |
| 2012年 | ロンドン・ビジネス・スクールへ留学 |
| 2017年 | MUFGのFinTech事業を独立させたJapan Digital DesignのCEOに着任 |
| 2021年 | SOMPO Holdingsデジタル戦略部チーフエバンジェリストに着任 |
| 2024年 | ネオファースト生命保険 代表取締役社長に着任 |

直近では、2021年からSOMPOホールディングスでデジタル領域の新規事業を担っていましたが、もともとは銀行マンをしていました。新卒で入行し、支店業務や社内のいくつかの部署を経験したのち、紙の手形を電子化するサービスを企画して、初めて事業の立ち上げというものを経験しました。このときの企画は日本初の電子手形サービスとなって全国へ広まり、収益として80億円にもなる大きな成果を得ました。これを機にロボットやバイオテクノロジーなど、様々な分野のスタートアップを支援するようにもなりました。
銀行、デジタル、生命保険と、一見すると繋がりのない分野を横断してきたように見えるかもしれませんが、普及していないサービスや技術、ビジネスなど、常に「新しいこと」へ挑戦を続けてきて今日に至ります。

思い返してみると、銀行員時代に、企業や市場の情報収集をする「調査部」という部署に配属されたことが、最初に「経営」へ興味を抱いたきっかけでした。
たくさんの経営者に直接話を聞きにいくのですが、素人同然の僕はたった数分で話題が尽きてしまって、しどろもどろ。「コミュニケーション力はある方」などと楽観視していたのに、上司に頼りきりになってしまうのが情けなくて、悔しくて。それから150冊のビジネス書を読み込んで、経営、経済、各種業界について猛勉強しました。
企業のトップに立つ人には、皆それぞれの理想や、物事の捉え方、考え方、進め方があります。時間をかけて夢を叶えていく様子を間近で見て学ばせてもらえたことで、僕も自分なりのアイディアを持つことができるようになりました。
そして、銀行員時代に電子手形のサービスを考案したときには、自分のアイディアで事業がどんどん大きく展開していくという体験に格別なやりがいがあることも知りました。
幼少期の夢は「パイロット」で、学生の頃は「建築家」を志し、就活では「商社マン」に憧れていて、若い頃は、今日のように自分が経営者というポジションに立つとは思っても見ませんでしたし、業界未経験の僕への今回のポジションのお声がけには驚きましたが、責任ある立場でまた大きな挑戦ができるならと、迷いなく手を挙げました。
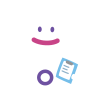
例えば、営業手法は想像以上に“昭和的”なスタイルが維持されていて驚きました。
現代のネット上での営業方法の多くは、まずは市場調査をして具体的なお客様像を絞り込み、次にSNS投稿や広告で情報提供をして少しずつ商品へ興味を持っていただけるように促します。そこからダイレクトメールやお電話で個別にご連絡を試みて、さらに進めたら店舗に足を運んでいただいたりご自宅へ伺ったり......というふうにステップを踏んで緩やかに進めていくのですが、保険の営業は未だに最初から「営業マンと面談」が一般的。一人ひとりのお客様に向き合って最高のものをご提案するというやり方は、ホスピタリティの面では素晴らしいのですが、営業する側・される側双方に心理的負担が大きく、属人的で、継続も難しい。
また、着任早々に驚いたのは、社内会議中の部屋がずっと真っ暗だったこと。
古いプロジェクターを使って資料を投影するために会議室内を暗くしていて、参加者は各々の手元で小さなスタンドライトを当てて紙の資料を読んでいたんです。相手の顔も見えない暗闇の中で活発な議論が展開するはずありませんよね。
このように「当たり前だから」と旧態依然の部分が多く、全体的に「装備は平成、心は昭和」という印象を持ちました。とりいそぎ部屋の明かりをつけて、会議前にアジェンダでの議題共有を必須化し、会議時間は原則30分以内に。着任直後は、業務の土台を令和バージョンへアップデートするところから始めました。
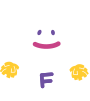
7〜8年前、海外旅行中に転倒して頭から血が出たので、現地の病院で処置してもらったことがありました。出血といっても大したことはなくて、医療用ホチキスのようなものでパチっと止血してもらい、病院での滞在時間もトータルで2〜3時間程度の軽傷だったのですが、帰国してから送られてきた請求書には「請求額120万円」と書かれていて、目玉が飛び出そうになりました。救急車の申請費用、医師の診察代、病院のベッドの使用料金など、それぞれが驚くほど高額で、どんどん加算されていくんですよね。加入していた保険で全額がカバーされて、胸を撫で下ろしました。
僕の場合は「旅先での事故」でしたが、通勤・通学中の事故や、突発性の病気など「予期せぬこと」は本当に誰にでも起こりうるんだなと実感した出来事でした。

「生命保険」のもととなる語句は、英語の“life insurance(ライフインシュランス)”なのですが、僕はこの「ライフ」という単語を「生命」から「人生」に訳し変えたいと考えました。
「生命」というと、例えば「がんで余命宣告をされたら何万円」など、生きるか死ぬかの瀬戸際になって初めて効力があるような「一瞬のための保険」というイメージがしませんか?
保険が、予測できない未来の一瞬に向けて長期間お金を払い続けるものだとすると、若い世代であればあるほど、必要性を感じにくいのではないでしょうか。
一方で「人生」は、生きている間ずっと、という「継続的な保険」のイメージです。
例えば、ちょっとした怪我をして数日間入院することになったとします。突然のことだったから自宅と病院をタクシーで往復した、食事を作れなくてテイクアウトやデリバリーを利用した、小さい子供がいたから託児サービスを依頼した......など、病院以外の場所でもいろいろとお金はかかってしまうはず。退院後に保険の請求をしてある程度の額が戻ってくるとしても、突然の、目の前の数万円の出費で、たちまち生活が立ち行かなくなることもありますよね。
「がんになったら」「亡くなったら」など「万が一の不安」より、もっと身近で小さな心配ごとが「人生不安」。日常生活の中で生じた「人生不安」を気軽に相談できて、そのとき必要なサービスの紹介もしてくれる。そうした存在になることを目指して「小さな人生不安にも、向き合う保険サービスを。」としました。

社員との対話の場でも「上原さん、普段は何をしてるんですか?」ってよく聞かれるんですが、これがいたって普通でつまらないんですよ。
最近はよく妻と一緒にショッピングや映画に出かけます。まとまった時間がとれれば旅行にも。これまでずっと365日仕事一辺倒で、家事も子育ても任せきりにしてしまったので、妻の心が離れていかないように努力するばかりです。
日課は、最近再開した毎朝5キロのランニング。趣味らしい趣味は、草むしりです。庭に生えてくるドクダミ草と一人で黙々と向き合っていると、ゾーンに入ったみたいなまっさらな状態になって、不思議と1時間でも2時間でもあれこれ考えずに無心になれるんです。
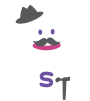
特定の誰かを目標に追いかけてきたということはないのですが、銀行員として最初に配属された支店で出会った支店長の「大きい判断こそシンプルに」という考え方は、今も僕が意思決定するときの根幹になっています。
組織のトップに立つ人には、例え6〜7割ぐらいしか必要な情報が揃っていなくても、重要な判断を下さなくてはいけない瞬間が、頻繁に訪れます。そんな、見通しが悪くて迷った時は「なぜ」を繰り返すんです。なぜこれをするのか、なぜ今するのか、なぜ自分は迷っているのか......など、原点まで立ち戻って様々な「なぜ」を頭の中で整理していくと、自ずと選択肢が絞られていきます。
直属の部下という立場でこの様子を見させてもらえたことは、僕にとって大きな財産になりました。
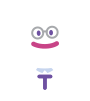
まずは、社内のみなさんへ。着任1年目の2024年度は、昨年度からの引き継ぎがメインの言わばゼロ段階。今後は、システムの構造改革を始め、CRMの刷新や、新たな人材の採用など、既存の枠組みや慣例を超えて良いと思う方向へどんどん会社を変えていくので、みなさんも変化を恐れず、新しいツールやシステムはどんどん試して、慣れて、挑戦してください。
在職期間が長くなると、知識や経験が増していくぶん、誰でも排他的・閉鎖的になりやすいものですから、社内の全員が最高のパフォーマンスを発揮できる「良い組織」の基本は、コミュニケーションだと思っています。
僕は何かひとつずば抜けた技術や知識を持つ専門家ではありませんが、これまでのキャリアの中で、前線に立つ仕事も、裏方で黙々と作業する仕事も経験してきたので、コミュニケーションを通して、点在する人材や技術、仕組みを融合させて最適化するのが得意な「組み合わせのプロフェッショナル」を自負しています。
僕のことは「社長」ではなく「上原さん」と気軽に呼んで、どんどん意見してください。おかしいなと思うことはビシバシ指摘してください。「こんなものができたらいいのでは」というアイディアも、大歓迎です。
そして、当社をご利用いただくお客さま、当社の商品を取り扱ってくださる代理店の皆さま。いつも、誠にありがとうございます。私たちは、10周年の節目を迎え、さらなる進化を目指そうと変革の真っ最中です。より良いサービスをお届けするため、既存の枠組みにとらわれない新たな挑戦を始めています。皆さまに、満足・安心いただけるように努力を重ねて参ります。これからのネオファースト生命に、ご期待ください。
